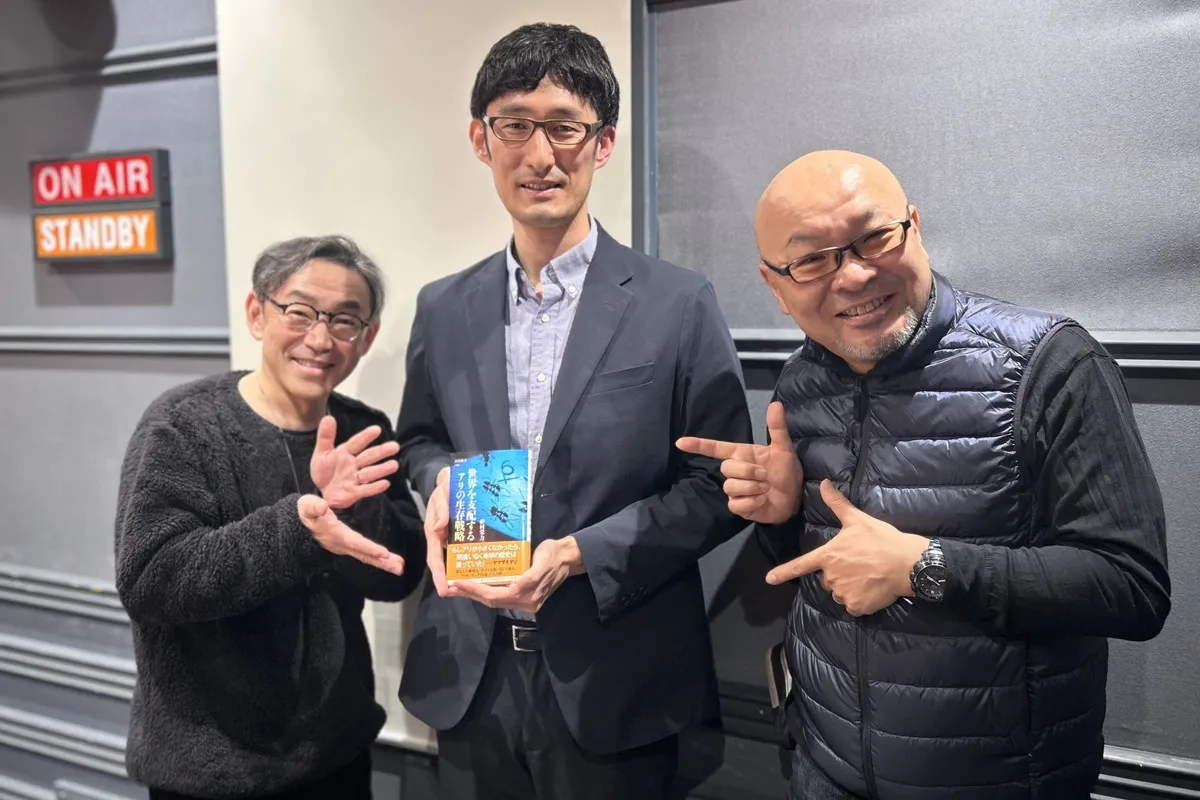未知の領域の趣味って、よく分からないことが多いですよね? その典型的な例が「服装」ではないでしょうか。たとえば登山やキャンプをやったことのない人間からすれば「季節や気温によって、いったい何を着ればいいの?」とちんぷんかんぷんですが、スポーツバイクも同じです。
サイクリストの服装は、基本的に薄手でピチッとしているので、初心者には「どれも一緒に見えるけど…」と思うのも不思議ではありません。しかし! 実は服の機能やスペックは細分化されており、気温や天候によって使い分ける必要があります。服装の選択を間違えると、暑すぎて汗だくになったり、寒すぎて凍えたりします。特に季節の変わり目は注意点も多いので、そのことを中心に解説します。

冬から春にかけてのウェア選びとコツ
冬から春にかけては徐々に暖かくなり、サイクリストにとってうれしい季節です。厚手のジャケットを着ていると途中で脱ぐに脱げません。ジャケットは生地が薄いものを選び、ウインドブレーカーやジレ(ベスト)でのレイヤリングで対処するのがコツです。
サイクリング出発時に「暖かくて快適」と感じるようだと、着込み過ぎのサインです。なぜなら、ひとたび走り出せば発熱してすぐ暖かくなるからです。出発時は「やや寒いが、耐えられるかな」くらいの格好で、どうしても寒ければウインドブレーカーを羽織り、途中で脱ぐのもアリです。

春から夏にかけてのウェア選びとコツ
春から夏にかけてのウェア選びは、どちらにせよ暖かい季節ですし、寒さに凍えることもないので、あまり心配は無用でしょう。基本は半袖の夏用ジャージ上下でOK。保険でアーム&レッグウォーマーを足すくらいで十分です
アームウォーマーは二の腕から手首までの保温のために使い、レッグウォーマーは太ももからふくらはぎの保温のために使います。メリットはどちらも「暑ければ脱げて、寒ければ装着できる」点です。コンパクトに折りたたんでバックポケットに入れられるので、脱いでも邪魔になりません。

夏から秋にかけてのウェア選びとコツ
夏から秋にかけての服装の基本は、薄着の夏用ジャージ上下でOKです。ただ、10月前後の秋口だと夕方と朝方は半袖だけだと寒い日もありますので、アームカバーとレッグウォーマーがあると安心できます。寒がりな方は保険でウインドブレーカーかジレを持参しておきましょう。真夏でも標高の高い山に行くなら、山と麓では気温差があるので必ず持っていくことをおすすめします。
筆者は真夏の8月に富士山五合目に上ったことがあります。スタート地点の河口湖駅は夏の格好で出発したのに、上るにつれて気温が下がり、五合目地点で気温13℃になった経験があります。秋用ジャケットを持っていって正解でした。

参考までに、 「100メートル標高が高くなると、気温は0.6℃下がる」と言われています。つまり標高が1000メートル高くなると6℃、1500メートルも高くなると9℃下がるという計算です。2300メートルだと約14℃も変化します。標高と気温の変化に加えて、ダウンヒルでは風をモロに受け続けるので、一気に体温が下がります。そうした意味でも、やはり1枚羽織るものがあるだけで体感温度が違うように思います。
秋から冬にかけてのウェア選びとコツ
最も注意したい季節が秋から冬にかけての時期です。防寒対策がしっかりしていないと、出先で後悔してしまいますので、天気予報は前日の晩と当日の朝に入念にチェックしましょう。暑ければ脱げばいいし、日陰で休めばしのげますが、寒さばかりはいかんともしがたいです。寒さで凍えてしまうと走れず、その場にも留まることもできないので、どちらにせよ大変です。

着ている服のほかに、保険でジレかウインドブレーカーをバックポケットに入れておくのが賢明です。
最後に筆者の目安も紹介
参考までに、筆者のウェア選びも紹介しましょう。大まかに6つの温度帯を設けて着るものを決めています。
・5℃以下:冬用ジャケット、冬用ビブ、冬用インナー、真冬用グローブ、シューズカバー、ウインドブレーカーで完全防備
・6~10℃:冬用ジャケット、冬用ビブ、冬用インナー、秋用グローブ(保険でジレ持参)
・11~15℃:秋用ジャケット、夏用ジャージ、秋用グローブ(保険でアーム&レッグウォーマーとジレを持参)
・16~20℃:夏用ジャージ、夏用ビブ、夏用グローブ、アーム&レッグウォーマー(保険でジレを持参)
・21~25℃:夏用ジャージ、夏用ビブ、夏用グローブ(山に行くときのみジレを持参)
・26℃以上:夏用ジャージ、夏用ビブ、夏用グローブのみ
筆者は耳と太ももの寒さは気にならないタイプなので、真冬でもこの部分が痛くなることがありません。理由は自分でもわかりません(笑)。寒さの耐性には個人差があるので、経験を積んで学んでいきましょう。