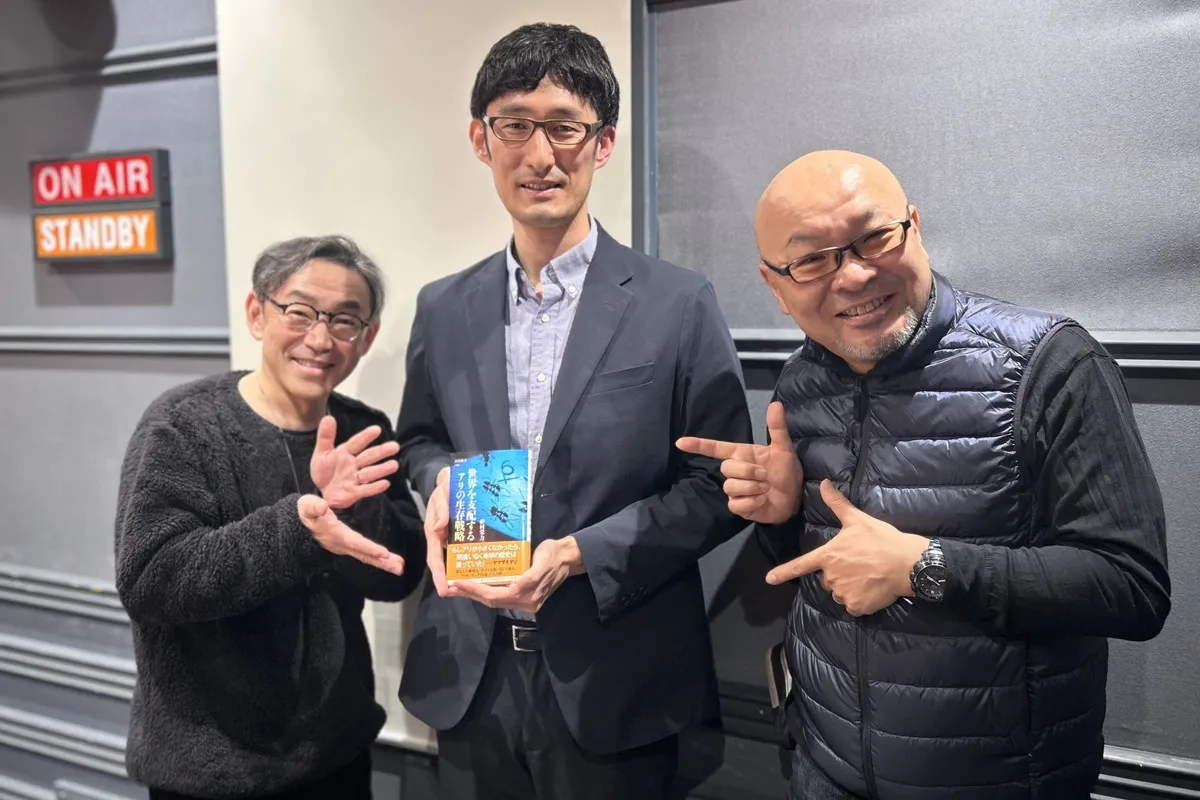ロードバイクでグラベルを走れる仕様にカスタムできる?自転車のカスタム特集<3>
ロードバイク界の昨今のトレンドといえば、タイヤが太くなったことです。10年前のロードバイクは23Cが標準。さらに細い、19~21Cだってありました。25Cは太めのタイヤでロングライド向け、という認識が一般的でした。しかし今やデフォルトは28C。「25Cが細め」という認識になり、プロレースでも30Cが使われたりします。ロングライド志向の「エンデュランスロードバイク」(※1)になると、大きなタイヤクリアランス(フレームとタイヤの隙間)が確保されるようになり、ロードバイクながら38Cまで装着できるモデルもあります。
※1:振動吸収性や速度維持力が高く、長距離走行向きのロードバイク

「太いタイヤが入る」=グラベルバイクではない
「38Cまで入る?ならグラベル用タイヤを装着して、グラベルロード(※2)としても使えるのでは?」
※2:グラベル(砂利道)と舗装路両方の走行を視野に入れた、長距離走行向けのロードバイク
そう考える人がいても不思議ではありません。普段は細めのタイヤでオンロード走行を楽しむ。休日は太いタイヤにしてグラベルライドに出かける。まさに一石二鳥。しかも、グラベル仕様にするにはちょっと太めのグラベル用タイヤに交換するだけでOK。お手軽にグラベルロード化できるような気がしますね。
しかし、そうは問屋が卸しません。「太いタイヤが入る」と「フレームやホイールが悪路走行に耐えられる強度を持っている」とは別のことだからです。

「ISO」(国際標準化機構)や「JIS」(日本産業規格)といった工業規格では、現時点でスポーツ用自転車として舗装路を前提とした「レーシングバイク」と、悪路を走る「マウンテンバイク」に分類されています。というか、その2種類にしか分けられていません。当然、舗装路のみを前提とした「レーシングバイク」より、悪路で飛んだり跳ねたりする「マウンテンバイク」(MTB)の方が強度が高く、頑丈に設計されています。
では、エンデュランスロードはどうでしょう。おそらく、メーカーは「舗装路を前提としたロードバイク」として設計しています。太いタイヤが入るからといって、悪路をガンガン走るスタイルに適しているわけではありません。軽い砂利道程度であれば問題ないとは思いますが、凹凸の激しいコースを走ると危険でしょう。F1マシンでラリーコースを走ったら壊れますよね。それと同じことです。
もしかしたらメーカーは「38Cまで入るのだから、ユーザーはグラベルを走ってしまう可能性がある。ちょっとだけ強度高めに作っとくか」という親切設計をしているかもしれません。しかし、そういう情報は私たちユーザーには届かず、判断できない。分からないので、太いタイヤが入るからといって「グラベル走ってもOKですよ」とは言えないのです。
関連記事自動車って、高性能になればなるほどタイヤが太くなる傾向にありますね。顕著なのがスポーツカー。一般的な自動車とは比べ物にならないほどの太いタイヤで地面を踏みしめている姿は、いかにも力強く速そうです。しかしロードバイクはその逆。

細分化されるロードバイク
前述の通り、かつてスポーツバイクは、ロードバイクとMTBに大きく二分されていました。舗装路用自転車と悪路用自転車の境目がきっちりしており、それなら「レーシングバイク、もしくはMTB」というざっくりとした区分でよかったのかもしれません。
しかし今は違います。ロードバイクが「ピュアロード」「エンデュランスロード」「オールロード」「グラベルロード」と細分化され、太いタイヤを履くようになりました。さらに、グラベルロードの中でも、舗装路を主眼に置いたモデルから「ほぼMTB」のような悪路性能を重視したモデルまで幅広い。そんなロードバイク市場が多様化している状況なのに、メーカーがどんな路面を想定して設計したのか分かりづらい。
世界的な規格設定機関による基準も登場
このような状況を受けて、メーカー側としても「この自転車はこんな路面まで耐えられるように設計しています」と分かりやすく伝える兆候があります。ここ数年で、「ASTMカテゴリー○準拠」という表記を行うホイールメーカーや自転車メーカーが出てきました。
ASTM(America Society for Testing and Materials)とは世界的な規格設定機関で、自転車に関しては使用状況別に以下の5つの区分が制定されています。「これが性能・品質を保証できる走行条件です」ということを示すものです。
●カテゴリー1:舗装路専用。タイヤが常に路面と接した状況を想定したもので、ロードバイク、タイムトライアルバイク、ツーリングバイク、クロスバイクなどがこれにあたる。
●カテゴリー2:舗装路に加え、起伏の少ない砂利道を想定したもの。15cm以内の段差に対応する。
●カテゴリー3:カテゴリー2よりも起伏の大きい路面や、障害物を乗り越えるような走り方に対応する。段差やジャンプの高さは60cm以内を想定。ハードテールMTBやショートストロークのフルサスMTBなど。
●カテゴリー4:かなり荒れた悪路を高速で走るフルサスMTB、およびMTB用ホイール。急勾配や過酷なトレイルでのジャンプにも対応する。ジャンプの高さや段差の落差は120cm以内。
●カテゴリー5:カテゴリー4以上に荒れた路面を走るための区分。ロングトラベルのサスペンションを装備したダウンヒルバイクやダートジャンプ用バイクなどがここにあたる。
かなり明確かつ細かく分けられているので、自分の楽しみ方に合ったバイクやホイールが選びやすくなり、これがカタログなどに掲載されるようになると、選ぶ側としては非常に良い目安になると思います。例えば、「砂利道を楽しみたいからカテゴリー2対応モデルを買おう」「よく走るコースにトレイルっぽいところがあるから、フレームもホイールもカテゴリー3のものを選ぼう」といった具合です。ぜひ参考にしてみてください。

自転車ライター。大学在学中にメッセンジャーになり、都内で4年間の配送生活を送る。現在は様々な媒体でニューモデルの試乗記事、自転車関連の技術解説、自転車に関するエッセイなどを執筆し、信頼性と独自の視点が多くの自転車ファンからの支持を集める。「今まで稼いだ原稿料の大半をロードバイクにつぎ込んできた」という自称、自転車大好き人間。
この人の記事一覧へ