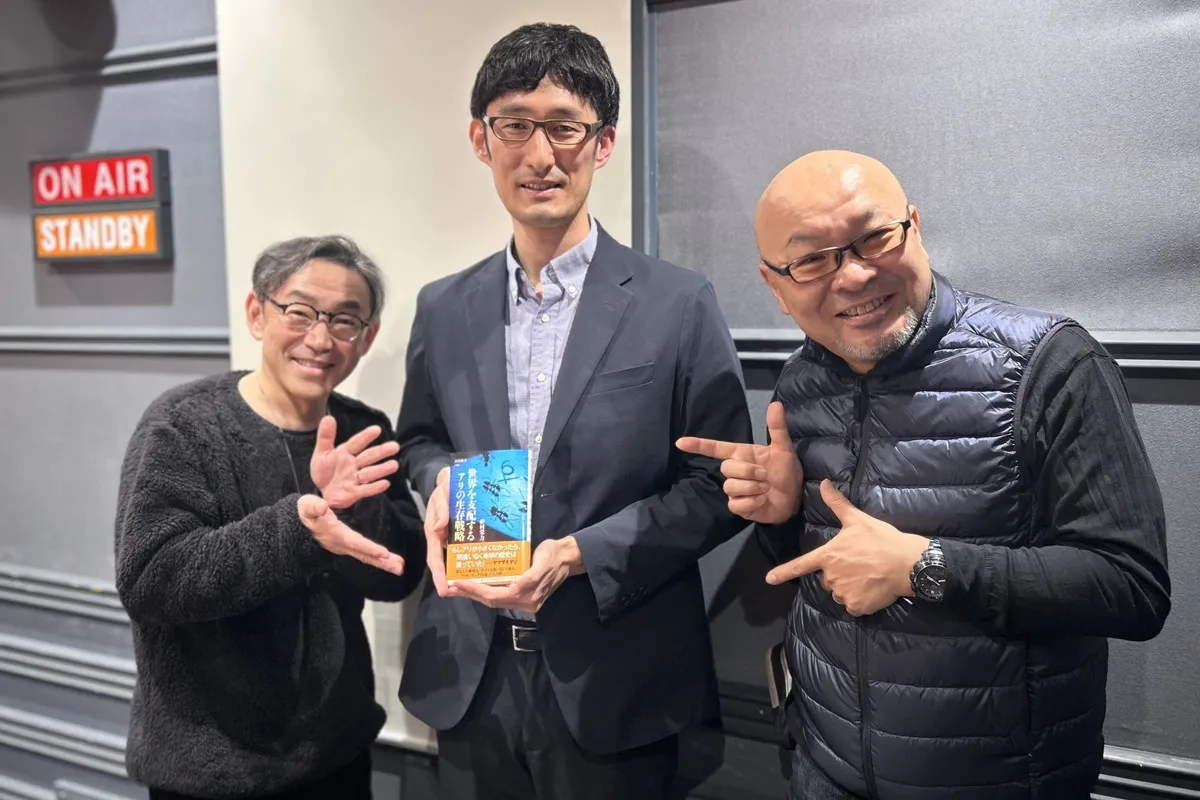「乗る」から「乗りこなす」へ ロードバイク“脱ビギナー”のステップロードバイクの選び方<5>
突然ですが、一つお聞きします。
「皆さんは自転車に乗れますか?」
日本人ならば、この質問に対して多くの人が「はい、乗れます」と答えるでしょう。日本は世界有数の自転車大国なので、大抵の人が幼少期から自転車に乗り始めます。キッズバイクも軽快車もロードバイクも同じ自転車なので、多くの人はなんとなくでも乗れてしまいます。

「乗れる」と「乗りこなせる」は大違い
しかし、軽快車とロードバイクは似て非なる乗り物。乗車ポジションも、変速操作も、タイヤの細さも大きく異なります。ハンドリングも、ブレーキングも軽快車とは大違いです。ビンディングペダルを使うなら、ペダルとシューズが固定されるという、さらに特異な要素が加わります。しかも軽快車の2~3倍のスピードが出ます。ロードバイクの場合、「乗れる」と「乗りこなせる」そして「安全に走れる」は大きな違いがあるのです。
ですので、ロードバイクに乗り始める際、まず乗ることに慣れるまでは決して無理をせず、ゆっくりと慎重に走るようにしましょう。できればサイクリングロードなど、クルマの往来がない場所で乗り慣れた人に教えてもらうと良いでしょう。
自転車はクルマにとって「忍者」
乗ることに慣れたら、クルマが行き交う車道を走ることになります。自転車もクルマと同じ車両ですから、道路交通法を守って走行するのはもちろんのことですが、ここで注意してほしいのが「自転車はクルマから見えにくい」という意識です。ロードバイクはクルマやバイクと比べて細くて小さいので視認しにくく、しかもエンジン音がしないので、車両として認知されにくいのです。クルマにとって車道を走る自転車は、まるでどこにいるかわからない「忍者」のような存在。死角に入ってしまうことも多く、接触したら確実に自転車側が被害を受けます。
そうならないために、明るい色のヘルメットやウエアを着用する、昼間からヘッドライトとテールライトを点灯させる、などの対策によって被視認性を上げる努力も必要ですが、「クルマから我々自転車は見えていない」という意識を常に持ち、自ら車間距離等の“安全マージン”を多めにとって走ることも重要です。
集団走行は事前に訓練を
ロードバイクに乗り慣れてくると、仲間と一緒に走る機会が訪れるかもしれません。複数人が集団になって走る「グループライド」です。

このグループライド、前走者の後ろについて走るため、空気抵抗が減り、速く遠くまで走れるようになります。また、仲間が一緒なので知らないルートでも安心ですし、トラブルが起きたときも助け合えるなど、メリットがたくさんあります。しかし、一人で走る単独走行とは違ったテクニックが必要となります。
前走者の背中やタイヤを凝視してしまいがちですが、前方の状況を把握しづらくなるため、前走者の肩越しに前を見るようにすること。急ブレーキ時に追突してしまわないよう、十分な車間距離をとること。自分の後ろにもライダーがいる場合、急ブレーキは急ハンドルなど、“急”が付く動作は避けること、などなど。これ以外にも「右左折」、「停止」、「障害物に注意」などを後続車に伝えるハンドサインも必要になります。緊急時には声を出して危険を後続に知らせることも大切です。
昔はロードバイクに乗る人はショップに所属するのが当たり前だったので、ショップの練習会などでグループライドのテクニックが自然と身に付いたものです。しかし、昨今は通販でものが買えたりネットで情報が得られたりと、自転車ライフが一人でも完結させられてしまう時代です。
しかし、グループライドは実際に経験しないとなかなか慣れません。ショップ主催のライドなどに積極的に参加して、グループライドのテクニックを身に付けておきましょう。仲間と一緒に走ると、自転車の世界が2倍にも3倍にも広がります。

自転車ライター。大学在学中にメッセンジャーになり、都内で4年間の配送生活を送る。現在は様々な媒体でニューモデルの試乗記事、自転車関連の技術解説、自転車に関するエッセイなどを執筆し、信頼性と独自の視点が多くの自転車ファンからの支持を集める。「今まで稼いだ原稿料の大半をロードバイクにつぎ込んできた」という自称、自転車大好き人間。
この人の記事一覧へ